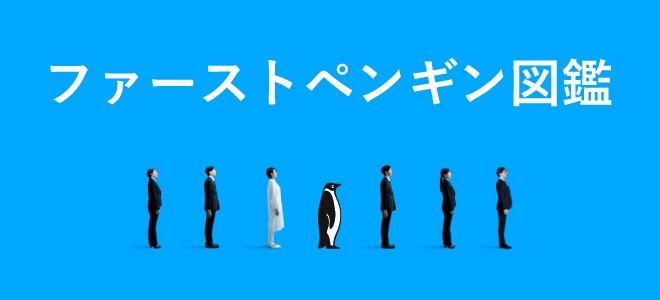富士化学社員によるクロストーク
FIRST PENGUIN
INTERVIEW
あなたはどんな
イノベーションを
起こしましたか?


ーあなたが関わったイノベーティブな仕事について教えて下さい。

一番印象深いのは、今まで富士化学で取り扱ったことのなかった「新規剤型の製剤開発」に携わらせてもらったことですね。それまで開発に携わったことのあった錠剤や顆粒剤の考え方とは異なる点も多く、その剤型に関して知識のある人が社内にほとんどいなかったので、最初は手探り状態で苦労しました。

製剤開発は、開発から承認まで数年単位で時間がかかるのが当たり前の世界ではありますが、その状況の中でどのように進めていったんですか?

考え込まずに、まずやれることをやってみようと思いました。実験室に立って試作をしたり、分析を担当したり。もちろん失敗もたくさんありましたが、得られる気づきもありました。
あとは、全員がほぼ0からのスタートだったので、臆さず意見したり、疑問に思ったら口にするようにしていましたね。実際、的外れではないかと思ってする素人的な質問も、意外と周囲の先輩方も同様に疑問に思っていた、なんて場面もありました。

私は原薬開発部なので仕事内容は異なりますが、実験室での検討は重要ですよね。

製剤開発部と原薬開発部、どちらも医薬品の開発に関わるお仕事ですが、
K.Hさんは原薬開発部でどんなお仕事されているんですか?

原薬開発部では、ジェネリック原薬を、実験室でg~数十gでの製法検討をした後、数十kg程度のスケールでの試作を経て、バリデーション製造※を行っています。(※バリデーション製造=プロセスの妥当性の検証、文書化)それをさらにスケールアップして、商用生産を行い、晴れて医薬品の安定供給への貢献につながるという感じです。
ただ、現場での製造では実験室での挙動と異なることが必ず出てくるので、その現象を詳細に分析し、不具合の原因を検証・特定し、その知見を基に実験室に戻って検討をやり直していました。


S.Mさんは開発とは全然違う職種ですが、どうでしょう?

イノベーティブな仕事と呼べるかわかりませんが、当社として初めてのサステナビリティレポートを作成した仕事が印象に残っています。
サステナビリティといっても、何がサステナビリティに該当する取り組みなのか、どのような構成でレポート作成すべきなのか、準拠や参考にすべきレポート作成のルールにはどのようなものがあるか等々..。
H.Rさんと同じくすべて手探り状態だったので苦労した覚えがあります。

新しい取り組みに対しては、はじめはどこの部署も手探り状態になりますね。
でもそのチャレンジングな姿勢を会社全体で持っているのが富士化学の魅力でもあると思います。

どの部署もそうですが、医薬品の安心安全は、地道な検討の積み重ねの上に成り立っているということを実感しますね。

ー 仕事を進める上で苦労したことはありましたか?
また、その困難をどのように乗り越えましたか?

製剤開発全般において苦労したことと言えば、化学や物理、工学、その他医薬品に関する規制など、使用する知識がすごく幅広いことですね。一方で、知識だけではなく経験で培われてくるちょっとした気づきや感覚が原因究明のきっかけになることも結構あり、戸惑うことも多かったです。
当時はとにかく実験室にいることが多く、周囲に相談しながら経験を積んで乗り越えたのが一番大きいです。皆さんはどうでしょうか?

私は品質保証部に所属しているのですが、監査対応や供給業者管理はいつも苦労します。なにより情報の整理、準備にとても時間がかかります..!
監査に関しては場数を踏むのもありますが、個人的には下準備が一番大事だと思っています。入念な準備をすることで、自分の回答に自信が持てるようになりました。

あと、ちょっと質問から脱線するんですが、監査自体は品質保証部のみで対応するわけでなく、他部署との連携がとても大切だと思っています。情報が分散していては準備に時間がかかるし、正確な情報を監査官に伝えることができません。
基本的なことではありますが、監査の信頼性向上、サプライヤーとの関係強化のため、部署での運用方法を把握したり、運用上での手順、記録はどうなっているのか理解したりなども常に心がけていることですね。


他部署との連携の話が出たので、私からも。
私が所属する経営企画室の仕事の多くは、社内や社外の専門家等多数のメンバーの協力を得ながら進める必要があります。特に、サステナビリティレポートの作成のような、当社として過去に経験のない仕事を進める場合には、その目的や意義などを、協力を得たい部門に対し丁寧に説明し、納得してもらう必要があります。
どの部門も既存の仕事を抱えている中、納得を得るのは簡単なことではありません。
また、取り組みの目的や意義を心から腹落ちしてもらわないと、得られる協力の質が上がらないので、他部門の協力を要請する際には、丁寧な説明と納得感の醸成を心がけています。

S.Mさんは、海外グループ会社の管理なども担当されていますよね。
英語の勉強とかもされていたんですか?
ちなみに私は英語がとっても苦手だったのですが、今の業種では英語の登場場面が多々あるのでちょっとずつ英語を勉強中だったりします…。

富士化学に勤務してからは、実際に米国のグループ会社での海外駐在を経験しました。海外駐在中に会社のサポートもありMBA(経営学修士)の取得も果たせましたが、語学スキルは私もまだまだ研鑽中です!
新しいことに挑戦することは、それなりのリスクや苦労を伴いますが、会社の経営方針の策定や大型設備投資などの大きな意思決定に直に関わるれるのは面白いし、やりがいを感じますね。

ー 入社を考える人に向けてメッセージをお願いします!

富士化学工業は、地元富山に根差した温かく堅実な雰囲気がありつつも、海外事業を展開していたり、富士化学工業のような規模の中小企業では挑戦しづらいような事業にも挑戦したりと、チャレンジングな姿勢も持っている点が私にとっての魅力の一つです。「挑戦」と聞くと不安に思う方もいるかもしれませんが、周囲のサポートがあるので、安心して働ける環境だと思います。今後、新しく入社される皆さんに刺激をもらいながら、一緒に成長していけたらと思います。

私の行っている品質保証業務は一見地味にみえるかもしれませんが、消費者の安心や会社の信頼を守る非常にやりがいのある仕事です。また日々新しい知識を得る事が出来る業種と思います。品質保証業務に限らず仕事全般についてですが、富士化学は皆さん仕事にまじめに取り組まれています。富士化学は入社後、自分を成長できる土壌であると思います。周囲と協力しながら自分の工夫を活かし、会社と一緒に成長していく楽しさをぜひ味わってほしいです。

当社は社員が何千人もいる大企業ではありません。大企業では専門部署を設けて対応しているような仕事も、当社では数名のチームで進めることがよくあります。良く言えば、幅広い業務経験を積む機会が、大企業に比べて圧倒的に多く、それだけやりがいも大きい。もちろん、各業務の専門性が大企業に比べて劣る部分はあるかもしれませんが、それは自分次第です。自ら学んで、いくらでも専門性は深められますし、そのためのサポートを会社は提供してくれます。幅広い業務を経験し、スキルを磨いていきたい、チャレンジしたい方には、とても良い会社だと思います。

この会社では医薬品の開発段階から製造まで、いろいろなことができると思います。新たな製造技術の探索、導入も積極的に行っていて、日々学ぶことも多い環境です。理系の知識を生かして医薬品の製造に携わりたいという志があれば活躍の場は広いですので、ぜひ皆様の入社をお待ちしております。